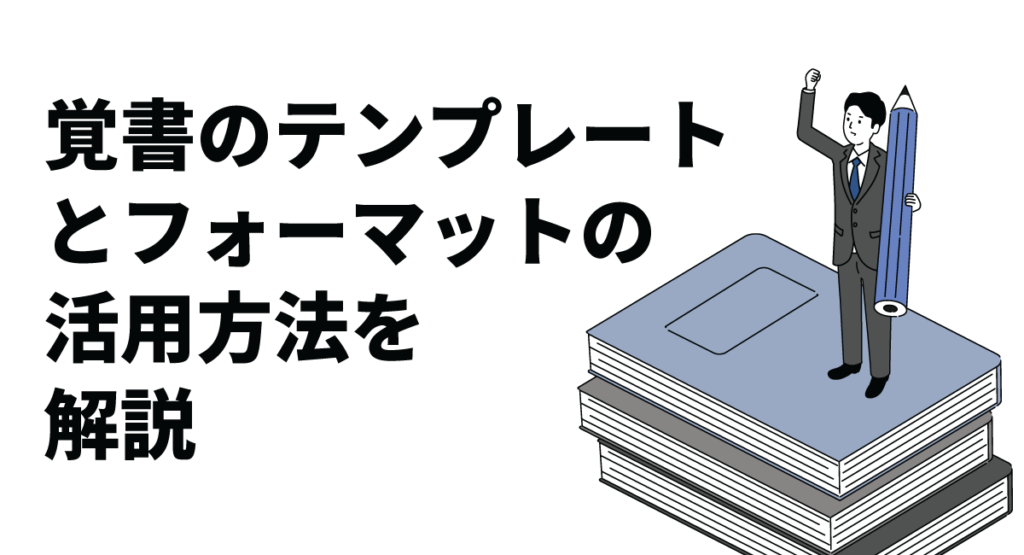
不動産取引では、契約書以外にも覚書を作成するケースがあります。覚書は、契約の合意内容を明確化し、トラブルを防ぐために作成される書類です。法的効力もあるため、高額な取引となる不動産取引の安全性を高める効果に期待できます。
今回は、覚書の基本知識や類似する書類との違い、不動産業界での活用方法、記載する項目・テンプレート、作成のポイントなどについてご紹介します。
覚書とは?

覚書(おぼえがき)は、当事者間で合意した契約内容を証拠に残すために作成する書面です。事前に契約内容を決めた場合、後日正式に契約書を締結する際に、契約内容に関して「言った・言わない」といったトラブルが発生する可能性があります。しかし、契約内容に双方が合意したことを記録に残しておけば、トラブルを防ぐことが可能です。
覚書はさまざまな取引・契約で活用でき、不動産取引でも用いられています。不動産取引では、隣家との境界線や接道、手付金の扱いといった確認・すり合わせが必要な事項が多いです。そのため、当事者間が決めた重要事項は口約束で済まさず、覚書によって合意の事実を証拠として押さえておくことが大切です。
覚書の法的効力
覚書には法的効力がありますが、単純に「覚書」というタイトルがついているだけでは、その効力は発揮されません。覚書に法的効力を持たせるためには、記載内容が重要となります。
具体的な権利・義務・違反に対する罰則など、細かく重要事項が記載されている状態であれば、法的拘束力を有する書類と認められます。しかし、事実関係や合意内容を簡易的に記録しただけのものであれば、法的拘束力は弱くなる可能性が高いです。
したがって、覚書に法的効力があるかどうかはタイトルで判断するのではなく、書面の内容を確認して判断する必要があります。
覚書と類似する書類との違い
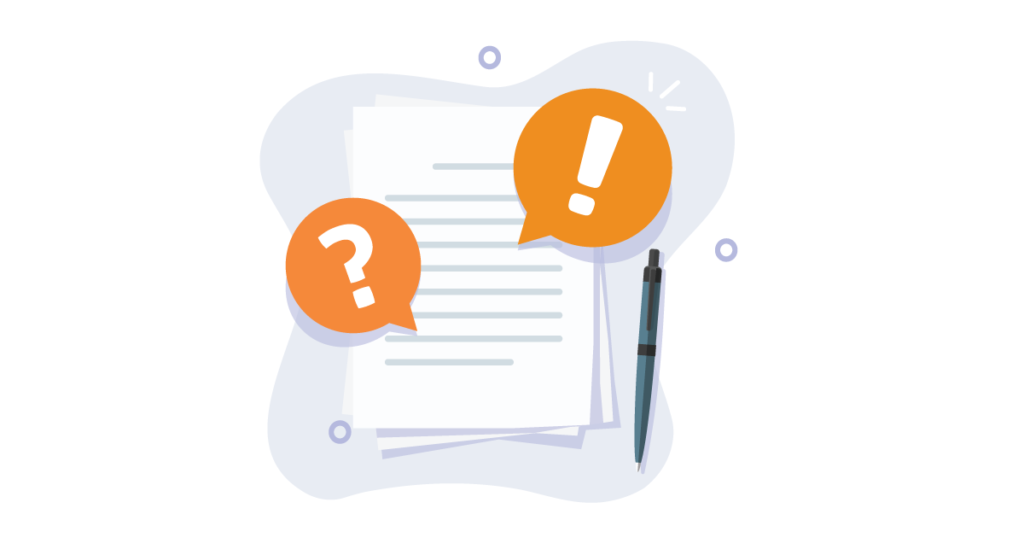
覚書と似通った書類として契約書・念書・合意書が挙げられます。ここでは、覚書と類似書類との違いに加え、それぞれの特徴などについてご紹介します。
契約書との違い
契約書は、民法552条1項において「当事者同士の意思表示が合致することで成立する法的効果が発生する契約内容を記載した文書」と定義されています。片方が契約を守らなかった場合、履行請求や契約解除などが可能です。
義務を履行しない場合、訴訟を起こして勝訴すれば、強制執行することもできるため、非常に強い法的効力のある書類と言えるでしょう。
一方の覚書は、合意した契約内容を記録するメモのような位置づけであり、契約書の内容を裏付けるための書類と言えます。しかし、取り決めた契約内容を双方が合意する意思表示をする内容であれば、覚書であっても契約書と同じく法的効力を持ちます。
念書との違い
念書は約束や義務を記載し、証拠として残すための書類です。覚書との違いは、当事者のどちらかが作成・署名・捺印し、もう一方に渡すことで双方が合意したことになる点です。
また、覚書は当事者の双方で書類を保管するのに対して、念書は受け取った側が保管することも相違点です。なお、一方の意思のみが記載される念書ですが、覚書と同じく約束したことを証明する効果があります。
合意書との違い
合意書も覚書と同じく合意内容を記録する書面で、当事者同士が署名・捺印すれば、契約書と同じ法的効力を持ちます。どちらも役割や法的効力に大きな違いはありませんが、作成する目的や利用シーンが異なります。
合意書は、偶発的・単発的に起きた事象における合意内容を記録し、証明する目的で作成されることが一般的です。一方の覚書は、正式な契約前に合意内容を記録するもののため、既存の契約の補足を目的に作成されます。
不動産取引で覚書が必要なケース

不動産取引で主に覚書が必要となるケースは、締結した契約の変更および契約後に条件を決める際の2つです。
締結した契約を変更する場合
すでに締結している契約内容を変更する際に覚書が作成されます。取引内容や条件を変更したり、新しい項目を追加したりする際に覚書を取り交わすことで、変更内容の合意を証明することが可能です。
覚書のフォーマットには特に決まりはありませんが、契約内容の変更を証明する書類のため、重要事項を具体的に明記することが求められます。
契約内容の変更で覚書を作成する場合は、タイトルを「変更契約書」や「変更確認書」とすることがありますが、役割や効力に違いはありません。
契約後に条件を決める場合
契約締結後に具体的な条件を決める際にも覚書が作成されます。
契約書には金額や作業範囲などの内容が記載されており、その内容で締結することが一般的です。しかし、実際に作業を始めてみないと作業量や範囲がわからないことに加え、細かい事前調査が必要な場合などもあり、締結時点で金額や条件などが確定できないケースがあります。
この場合、後から確定した合意内容であっても覚書で取り決めておくことにより、既存の契約を補うことが可能です。なお、契約締結後に覚書で補う場合は、契約書に「○○は別途協議の上で定める」といった文言の記載が必要になります。
覚書の主な項目・テンプレート
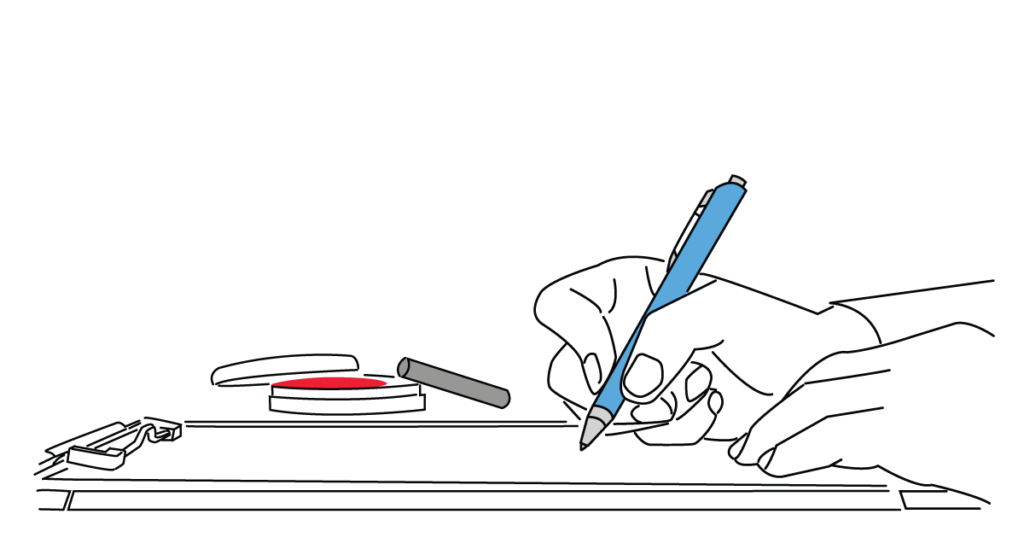
覚書に決まったフォーマットはありませんが、盛り込んでおくべき項目がいくつかあります。特に法的拘束力を持たせたい場合は、具体的に合意内容などを記載し、双方の署名や捺印も必要です。覚書の作成で必要となる主な項目は以下のとおりです。
- 表題
- 前文
- 本文
- 有効期限
- 後文
- 日付と署名・捺印
以下に各項目の記載内容・テンプレートを紹介します。
表題
表題には、「覚書」と記載します。できれば「○○に関する覚書」と記載し、何に対する覚書なのかを一目でわかるようにします。具体的なタイトルにすることで、認識の相違を小さくすることが可能です。
【例文】
土地売買契約に関する覚書
賃貸借契約に関する変更覚書
前文
前文では、契約に関わる当事者同士が覚書の締結によって合意することを記載します。ここでは簡潔に記載するために、「甲」や「乙」といった略称を使うことが一般的です。
その際、顧客や委託者などの何かをしてもらう側を甲、事業者や受託者といった何かをする側を乙と表記します。しかし、覚書や契約書を作成した側を甲、もう片方を乙とするケースもあり、甲乙に明確な使い分けのルールはありません。
なお、すでに契約書を締結しているときや関連書類がある場合は、覚書も契約書と同じ表記で記載するようにしましょう。また、いつ取り交わした契約書なのかを具体的かつ正確に記載します。
【例文】
○○○○○(以下「甲」)と●●●●●(以下「乙」)は、下記のとおりの内容に合意する覚書を締結する。
○○○○○(以下「甲」)と●●●●●(以下「乙」)は、令和○○年○月○日付で甲乙間が取り決めた「○○契約書」(以下、「原契約」)を、下記のとおり変更することに合意する覚書を締結する。
本文
覚書のメインとなる本文には、当事者間で合意した内容を箇条書きで記載します。前文の直下に「記」と記載し、その下に本文を記載していきましょう。
本文は「○○とする」といった文体で、なるべく内容を簡潔にし、本文の締めには「以上」と記載します。なお、契約内容の変更であれば、変更の違いを明記することを心がけましょう。
【例文】
1.原契約第4条(履行期間)に記載のうち
「本契約の契約期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間とする。」を
「本契約の契約期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間とする。」に変更する
2.乙は、甲に対して□□□□□ものとする。
3.本覚書に記載がない事項については、原契約書のとおりとして変更はないものとする。
以上
有効期限
覚書に有効期限を設定する場合、その期間を本文の下に記載することが一般的です。「有効期限は、○○年○月○日~○○年○月○日とする」と正確に記載しましょう。
【例文】
本覚書の有効期限は、令和7年4月1日~令和8年3月31日までの満2年間とする。
後文
本文の後に、後文として覚書の作成通数や保管方法、誰が何を保管するのかなどを記載します。
【例文】
以上、本合意を証するため、本書を2通作成又は本書の電磁的記録を作成し、甲乙両社が記名・押印もしくは署名又は電子署名の上、各自保管するものとする。
日付と署名・捺印
最後に当事者各々の署名・捺印の項目と、合意日や効力の発生日を記載します。
【例文】
令和○○年○月○日
(甲)氏名 ○○○○○
住所 ○○○県○○○市○○○町○-○-○ 印
(乙)氏名 ○○○○○
住所 ○○○県○○○市○○○町○-○-○ 印
覚書を作成する際のポイント
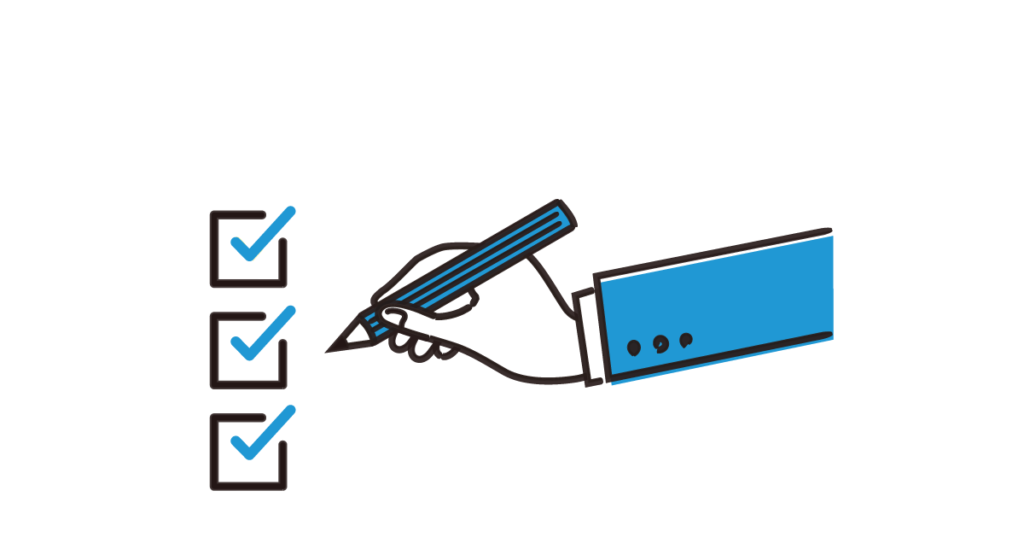
覚書を作成する際に押さえておきたいポイントは以下のとおりです。
- 合意、変更内容を明確に記載する
- 合意の確認を盛り込む
- 課税文書であれば収入印紙を貼る
合意・変更内容を明確に記載する
覚書は「誰が誰と何の契約をするのか」「何をどう変更したのか」など、合意内容や変更内容を詳細に記載することが大切です。曖昧な表現で記載した場合、誤解や曲解につながり、契約後のトラブルにつながる可能性が高まります。誰が見ても正しい内容で解釈できる文章であることが大切です。
このことは、覚書に法的効力を持たせるためにも重要なポイントです。無用なトラブルに巻き込まれないためにも、要件を満たした法的効力のある覚書を作成します。
合意の確認を盛り込む
合意内容だけではなく、その旨に当事者同士が合意したことがわかる一文も盛り込みます。例えば、「○○の内容について、双方に相違がないことを確認した」「今回の内容について確認し、相違がないことに同意しました」などの内容です。
このような確認を加えておくことで、当事者同士が合意に至ったことを証明できます。万が一、相手が合意していないと反論しても、覚書を証拠にできるのでトラブル回避につながるでしょう。確認事項だけではなく、日付・署名・捺印の項目も設けて法的効力のあるものにします。
課税文書であれば収入印紙を貼る
覚書に収入印紙の貼りつけが必要かどうかは、印紙税法別表第一(課税物件表)の課税文書に該当するかで変わります。不動産取引の場合、土地の賃貸借契約や建設協力金を定める賃貸借契約は課税文書となるため、収入印紙が必要です。しかし、アパート・マンションなど建物の賃貸借契約や電子契約による賃貸借契約においては非課税となっています。
課税文書かつ当事者間で課税事項を証明する目的で作成された覚書であれば、収入印紙の貼りつけが必要です。印紙税額は契約金額によって異なりますが、1万円未満であれば非課税となります。
なお、課税文書に収入印紙を貼りつけなかった場合は、脱税とみなされて罰則が科せられる可能性があります。脱税とみなされると過怠税が発生し、本来の印紙額を大幅に超える金額を納めなければなりません。
覚書は電子化することも可能

電子帳簿保存法によって、覚書の電子化が可能になりました。覚書の電子化によるメリットは以下のとおりです。
- 契約業務を効率化できる
- ペーパーレス化につながる
- 書類の検索とアクセスが容易になる
- 収入印紙の貼りつけが不要になる
電子化すれば、印刷や郵送、物理的なファイリングといった手間を省くことができ、作業を大幅に簡略化することが可能です。相手方に覚書を送る際も、メールの添付などによってコストをかけることなく、速やかに送信できます。電子署名システムを活用すれば、オンラインで署名することも可能です。
ペーパーレス化は、契約書の保存スペースを削減できるだけでなく、印刷代や収入印紙代などのコストも削減することが可能です。また、検索機能を活用して素早くファイルを開くことができるなど、管理がしやすいこともメリットと言えるでしょう。
電子化の際には、各種システムの導入や運用体制の構築などの手間やコストが短期的にはかかりますが、業務の効率化や負担軽減といった中長期的な効果が得られる点がメリットです。
仲介業務、賃貸管理業務の書類作成や管理に役立つ『いい生活のクラウドSaaS』

不動産の売買や賃貸の仲介、賃貸管理では、契約書や覚書などの各種書類を作成・管理する必要があります。そのような業務を効率化するのが『いい生活のクラウドSaaS』です。
『いい生活のクラウドSaaS』は、不動産業務を幅広く支援する以下のようなシステムを提供しています。
- 賃貸仲介:『いい生活賃貸クラウド One』
- 売買仲介:『いい生活売買クラウドOne』
- 賃貸管理:『いい生活賃貸管理クラウド』
これらのシステムを導入することで、契約書や査定書の作成、顧客・物件情報の一元管理が可能になります。また、不動産ポータルサイトへの一括掲載や販売図面・集合チラシの出力といった集客・営業支援機能も搭載されており、業務効率の向上やコスト削減に貢献します。
詳しくは資料をダウンロードいただくか、お気軽にご相談ください。
不動産取引のトラブル防止に覚書を活用しよう

覚書は、当事者同士の合意内容を証拠として残し、契約書を補完する役割を果たします。契約内容を事前に定めた場合や、契約書の変更が必要になった際に作成することで、トラブルの防止につながります。特に決まった形式はありませんが、内容を詳細かつ明確に記載し、日付や双方の署名・捺印を行うことで、法的効力を持たせることが可能です。
現在では、覚書を電子化することで収入印紙代を削減できるほか、管理の効率化も図れます。また、不動産仲介・管理における書類作成や情報管理は、システムを活用することでさらにスムーズになります。
『いい生活のクラウドSaaS』では、不動産業界の業務効率化に役立つ各種システムを提供しています。詳細については、お気軽にお問い合わせください。


