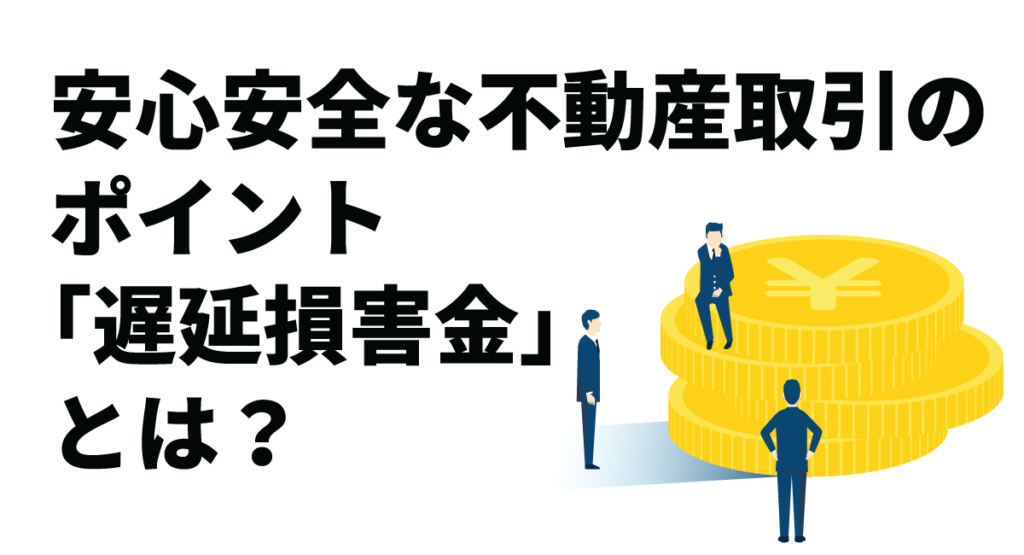
不動産取引で賃料や売買代金などの支払いが遅れた場合、遅延損害金が発生します。遅延損害金は不動産会社のキャッシュフローを悪化させるため、速やかな回収が必要です。
その一方で、回収方法を誤った場合の法的リスクもありますので、遅延損害金の発生を未然に防ぐ対策が求められます。そこで今回は、不動産取引におけるリスクを回避するためのポイントを解説し、遅延損害金の利率や算出方法、適切な回収方法などについてもわかりやすく解説します。
遅延損害金とは?
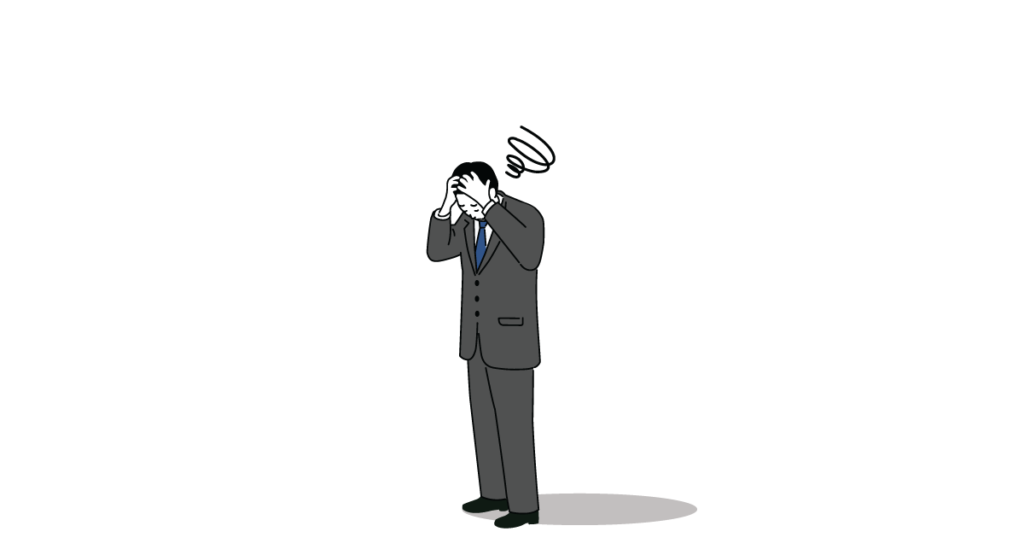
遅延損害金とは、金銭債務の履行が遅れた際、債務者が債権者に対して支払う損害賠償金です。不動産取引では、売却代金や家賃、管理費や違約金などの支払いで遅延があった場合、遅延損害金が発生します。
遅延損害金は契約書に定めた利率に基づいて計算しますが、契約書に記載がないからといって、支払義務が免除されることはありません。また、不動産取引は取引額が高額になるケースが多いため、それに伴って遅延損害金の額も大きくなる傾向にあります。
遅延損害金の利率
遅延損害金の利率は利息制限法に定めがあります。債務の額に応じた上限利率(年率)は以下のとおりです。
- 10万円未満:29.2%
- 10万円以上100万円未満:26.28%
- 100万円以上:21.9%
利率は契約書や約款などに定めるケースが多く、当事者間で合意した利率を「約定利率」といいます。不動産取引の場合、遅延損害金の約定利率は14%から20%が一般的ですが、住宅ローンは14.6%が相場です。
なお、遅延損害金の利率には「法定利率」もあります。従前は5%でしたが、2020年4月1日施行の民法改正で3%に引き下げられました。次の項目では、民法改正の背景について解説します。
民法改正の背景
法定利率の民法改正の背景には、バブル崩壊後の経済状況の変化があります。
改正前の旧民法は1896年に制定され、年利5%の固定利率制が100年以上続いていました。しかし、平成期のバブルの崩壊後は低金利政策が続き、ゼロ金利政策が実施されていた時期もあります。そのため、旧民法下の固定利率制では経済状況の変化に対応できなくなっていました。
そこで、実体経済に即した不動産取引などを実現・促進するために、2020年4月1日以降は法定利率を3%に引き下げられました。また、利率は固定ではなく変動制になり、法定利率は3年ごとに見直されます。そのため、法定利率で遅延損害金を計算する場合は、必ず現行利率を確認する必要があります。
遅延損害金の算出方法
遅延損害金は以下の計算式で算出します。
借入残高×遅延損害金利率÷365日(うるう年は366日)×延滞日数
例えば、2,000万円の住宅ローンで遅延日数が100日、利率が20%であれば、遅延損害金は以下となります。
2,000万円×20%÷365日×100日=1,095,890円
なお、分割払いについては、遅延した返済分のみ遅延損害金が発生します。住宅ローンの返済額が毎月10万円、遅延日数が60日、利率20%の場合は、以下の計算式で遅延損害金を算出することができます。
- 1カ月目:返済額10万円×20%÷365日×30日=1,644円(1円未満は四捨五入)
- 2カ月目:返済額20万円×20%÷365日×30日=3,288円
- 合計:1,644円+3,288円=4,932円
遅延損害金と利息の違い
利息とは、お金を貸し借りする際に元本の利用対価として発生する金銭です。遅延損害金は支払期日を過ぎると発生しますが、利息は借金をした時点で発生することが相違点です。
なお、遅延損害金は契約書に定めがなくても請求することができますが、利息は定めがない場合は原則として請求することができません。ただし、貸し借りの当事者が商人(法人や個人事業主)であれば、契約書に定めがなくても、法定利率3%で計算した利息を請求することが可能です。
遅延損害金額を適切に設定する
遅延損害金を契約書で定める際は、適正な利率の設定が必要です。不当に高額な遅延損害金を設定した場合、消費者契約法によって無効とされる可能性があります。特に、賃貸借契約の場合は、借主が著しく不利な条件を負わないよう、適正な利率を設定することが求められます。
滞納家賃の遅延損害金には利息制限法が適用されないため、14.6%を超える利率は消費者契約法の修正を受けます。例えば、遅延損害金の利率を14.6%超に設定し、貸主と借主が合意したとしても、実際に適用される利率は14.6%が上限です。
なお、借主が消費者契約法の適用を受けない事業者(法人など)であれば、遅延損害金利率の上限はありません。
不動産取引における遅延損害金

不動産取引においては、以下のような状況で遅延損害金が発生します。
- 不動産売買契約における売買代金の未払い
- 住宅ローンや不動産担保ローンの返済遅延
- 賃貸借契約における家賃滞納
一方的に売買契約を解除したときの違約金や、マンション管理費などの未払いも遅延損害金の対象です。遅延損害金には時効があるため、一定期間内に回収できなかったときは、請求権が消滅します。以下、具体例をみていきましょう。
不動産売買契約の場合
不動産の売買契約では、契約書に定めた期日までに売買代金の支払いがなかった場合、遅延損害金が発生します。契約解除の際に違約金が発生し、その支払いが遅れた場合も同様です。請求額は以下のように計算します。
- 売買代金の遅延損害金:売買代金×遅延損害金利率÷365日×遅延日数
- 違約金の遅延損害金:違約金×遅延損害金利率÷365日×遅延日数
不動産の売買契約における遅延損害金も、利率の上限は14.6%です。売買代金の遅延損害金は高額になるため、買主が「契約内容がおかしい」などと主張し、支払いを拒絶するケースも少なくありません。違約金は「売買代金の20%」に設定する場合が多く、遅延損害金と合わせて請求すると、さらに高額になるため回収が難しくなることが考えられます。
不動産ローン・借入の場合
不動産担保ローンの遅延損害金は以下の計算式で算出されます。遅延損害金利率は20%程度が一般的です。
不動産担保ローンの遅延損害金:請求金額の元本×遅延損害金料率÷365日×遅延日数
不動産のローンは金融機関との契約に基づいており、滞納期間や滞納回数によっては、担保の土地・建物が競売にかけられる場合があります。また、遅延損害金利率は、金融機関やローン商品によって異なるため、常に最新の情報を把握しておくことも重要です。特に、不動産担保ローンの場合、利率は担保評価や借入人の信用状況によって変動するため、個別の案件ごとに確認が求められます。
賃貸契約の場合
賃貸契約では、契約書に定めた期日までに賃料が支払われなかった場合、遅延損害金が発生します。マンションなどの管理費や退去時の修繕費用(原状回復費用)、契約更新料の支払い遅延も遅延損害金の対象です。その場合の損害遅延金は以下の計算式で算出されます。賃貸契約の場合、損害遅延金利率の上限は14.6%となります。
- 家賃の損害遅延金:家賃×遅延損害金利率÷365日×遅延日数
- 管理費や修繕費用の損害遅延金:未払い金額×遅延損害金利率÷365日×遅延日数
- 契約更新料の損害遅延金:更新料×遅延損害金利率÷365日×遅延日数
借主がすでに退去していると、遅延損害金だけでなく家賃や修繕費用の回収も難しくなる可能性が高くなります。また、更新料は当事者間の取り決めになるため、契約書に記載がない場合は回収が難しくなるでしょう。
遅延損害金が生じた場合の対応

不動産取引で損害遅延金が生じたときは、速やかな回収が必要です。回収不能となると、不動産会社が損失を被ることに加え、必要に応じて法的措置を取る場合は、訴訟費用や弁護士費用の負担が生じます。また、物件オーナーへの支払いが滞ると、信頼関係に悪影響をおよぼす可能性が高いです。そのため、遅延損害金を発生させない予防策、遅延損害金が生じた場合の適切な対応を把握しておくことが重要です。
ここでは、遅延損害金の適切な回収方法、事前の予防策などについて解説します。
事前の予防策を講じる
遅延損害金を発生させないためには、事前の予防策が大切です。契約書には支払期限と遅延損害金が発生する条件などを明記し、顧客に十分な説明を行うようにしましょう。
顧客とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を築くことも支払遅延を防ぐためのポイントとなります。重要事項を説明する際は、顧客が内容を理解できているかどうかのチェックも欠かさず実施しましょう。また、顧客が支払いを忘れないよう、期日前にメールやSMSを送信することに加えて、書面を郵送して注意喚起するといったリマインドも有効です。
また、言うまでもありませんが、不動産会社の担当者も期日管理を徹底することが求められます。社内でスケジュールを共有し、期日チェックを怠らないなどの対策が必要です。
家賃保証会社を利用する
賃貸物件を取り扱う場合は、家賃保証会社を利用するのも一つの方法です。家賃の滞納が発生した場合、入居者に代わって家賃保証会社が家賃を立て替えます。また、家賃保証会社は入居審査を行う際に、独自の基準で審査を行うため、滞納リスクを軽減することができるでしょう。
ただし、家賃保証会社の保証範囲や条件は、会社や契約内容によって異なります。保証会社に頼りきるのではなく、入居者に対して「滞納が続くと契約解除もあり得る」など、家賃滞納が発生しないように注意喚起しておくといった対策を講じておく必要もあるでしょう。
家賃保証会社については以下の記事でも解説していますので、参考にしてみてください。
関連記事:賃貸保証会社とは?審査の流れや費用相場、メリット・デメリットも解説
滞納発生時の対応を整理しておく
滞納が発生した場合の対応をあらかじめ整理しておくことも有効です。家賃滞納が発生した場合は、入居者に電話やメールで連絡を取り、いつまでに・どのような方法で支払うのかを確認することが必要です。
家賃の支払いを書面で督促する場合は、督促の事実が残るように内容証明郵便を使います。内容証明郵便を使うと、誰が誰に対し・いつ・どのような書面を送ったか証明できるので、訴訟に発展したときの重要な証拠になります。
また、入居者に支払猶予や分割払いを提案する場合は、提案に応じなかった場合も想定し、賃貸借契約の解除も視野に入れるなどの備えが必要です。最終的には財産を差し押さえるといったことも考え、弁護士や司法書士の手配なども検討しておきましょう。
督促は法令を遵守して適切に実施する
賃料や売買代金などを督促する場合、法令を遵守した適切な方法で進める必要があります。以下の方法で督促すると、違法行為とみなされる可能性があるので注意が必要です。
- 法定利率または契約で定めた上限を超える遅延損害金を請求する
- 勤め先に督促電話を入れる
- 玄関などに督促状の貼り紙を貼る
- 本人以外の人に家賃や代金を督促する
- 早朝や深夜に督促する(電話や訪問)
- 入居者の部屋に居座る
- 無断で部屋の鍵を交換する
高圧的な督促が問題視されると、損害賠償請求や行政指導の対象になる可能性があります。法律を遵守し適切な方法で回収し、自社の社会的信用を落とさないためにも注意が必要です。
契約書に遅延損害金の記載がない場合はどうなる?
契約書に遅延損害金の記載がない場合、法定利率が適用されます。利息制限法は、遅延損害金を支払うように定めているわけではないため、法定利率3%で請求すると、債務者が支払いを拒否する可能性があります。
しかし、約束したお金を支払わない「債務不履行」については、契約書に遅延損害金の定めがなくても支払義務が発生します。契約書に約定利率を定めていなかったときは、法定利率による遅延損害金を請求するようにしましょう。
支払いの滞納を防ぐためのポイント
遅延損害金の発生を防ぐためには顧客とのコミュニケーションを円滑化に加えて、契約管理の徹底が欠かせません。リソースが限られる中、効率よく契約・顧客を管理するのであれば、不動産業務のデジタル化をサポートするクラウドサービスなどを活用すると効果的です。
『いい生活売買クラウド One』は、不動産売買業務に最適化されたDX支援サービスです。顧客情報の管理、売買契約はもとより、売却査定や物件の広告から営業の成績管理まで、一連の幅広い業務の効率化をサポートします。最新の法改正に対応した重要事項説明書や売買契約書を利用することも可能です。
また、賃料の滞納による遅延損害金の防止には賃貸管理システム『いい生活賃貸管理クラウド』がおすすめです。賃貸借契約や入出金の管理はもちろんのこと、物件管理や入居者対応などの賃貸管理業務全般を一元管理することができます。紙やエクセルで行っていた属人的な賃貸管理業務をデジタル化することで、契約・顧客管理の抜け漏れやミスを防ぐことが可能です。
遅延損害金の理解を深め、不動産取引のリスクを軽減する
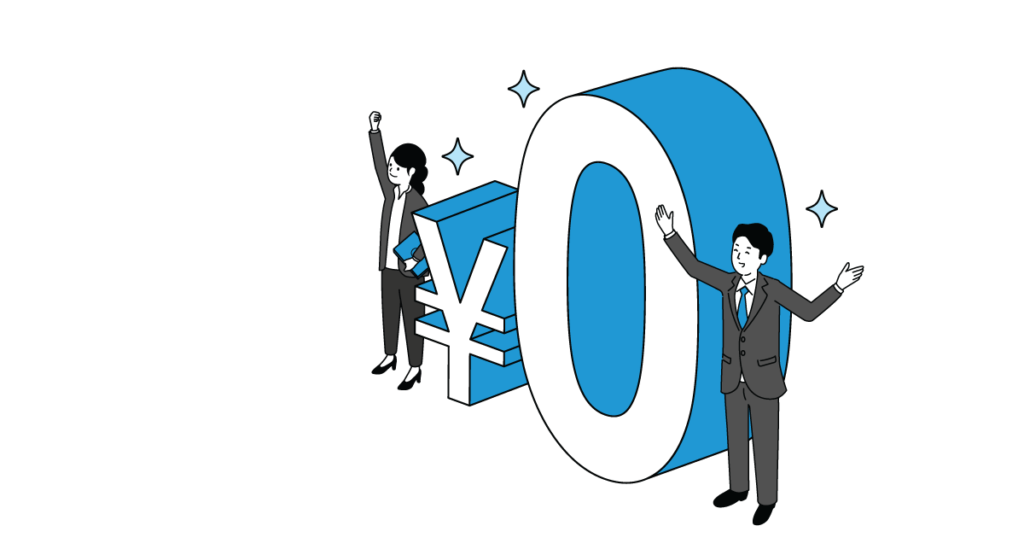
契約に基づく支払いが期日までに行われなかった場合に発生する「遅延損害金」。各種トラブルを未然に防ぐためには、その仕組みやリスクについての理解を深めておくことが大切です。また、支払いの滞納や遅延が発生した場合は、冷静かつ法的に適正な手続きを踏むことが求められます。円滑に回収を進め、不動産取引全体への影響を最小限に抑えることがポイントです。
遅延損害金の発生を防ぐためには、売買契約や賃貸借契約の管理の徹底、顧客とのコミュニケーションの円滑化が大切です。『いい生活売買クラウド One』、賃貸管理システム『いい生活賃貸管理クラウド』を活用し、不動産業務のデジタル化による効率化による契約管理の徹底をぜひ、ご検討ください。


