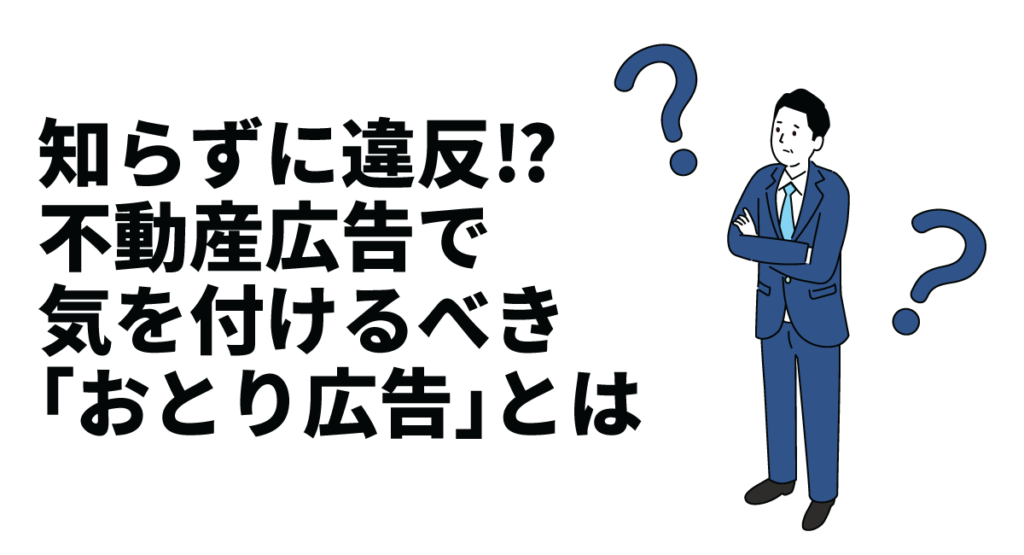
おとり広告とは、多くの顧客を獲得するために、実際には取引できない物件や商品を掲載した広告のことを指します。顧客の関心を引く物件であっても、実際に取引することはできないため、結果として顧客に不信や不満を与えてしまうことになります。
さらに、おとり広告は宅地建物取引業法に抵触する可能性があり、企業が法的責任を問われるといったリスクのある手法です。おとり広告を防ぐためには、法律の基準を理解した上で、誤解を招く広告表現を避けるためのポイントを把握しておくことが欠かせません。
そこで今回は、おとり広告とは何か、虚偽広告との違い、具体的な事例やリスク、そしておとり広告を回避するためのポイントについて解説します。適切な広告運用による適切な集客活動を実現するためにも、ぜひこの機会に理解を深めておきましょう。
おとり広告とは?
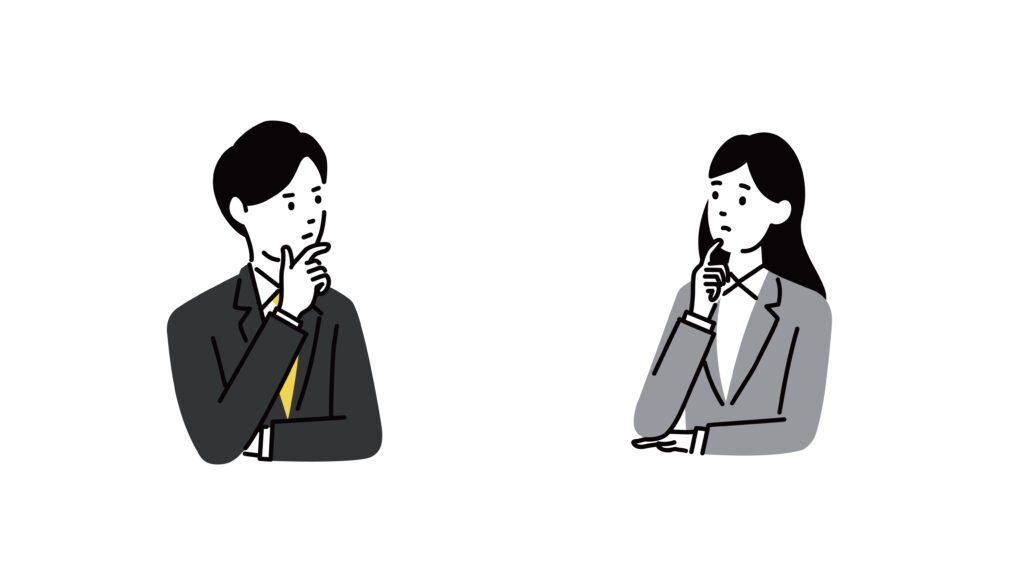
「おとり広告」とは、どのような広告を指すのでしょうか。ここでは、おとり広告の定義、虚偽広告との違い、おとり広告によるリスクについて解説します。さらに、実際にみられる代表的な事例についても紹介します。
おとり広告の定義
おとり広告とは、顧客を誘引する目的で、実際には取引できない物件やサービスを広告に掲載する行為のことを指します。不動産業界では、売買契約や賃貸借契約を成立させるために使われることが多いですが、他の業種でもみられるものです。
このような広告は、消費者を欺くものとして、宅地建物取引業法(宅建業法)や不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)で禁止されています。企業の社会的信用を失墜させる原因にもなりますので、注意が必要です。
虚偽広告との違い
「虚偽広告」は、実際には存在しない物件やサービス、あるいは事実に反する情報を掲載した広告を指します。
例えば、架空物件の掲載や、他の物件よりも優れていると誤認させるような表示、過剰に評価させた情報などを掲載したものが該当します。
おとり広告、虚偽広告のいずれも消費者を誤認させる違法な広告手法です。ただし、おとり広告は「販売するつもりがない」ものであるのに対し、虚偽広告は「そもそも事実でない」という点で異なります。なお、虚偽広告も、宅建業法や景品表示法違反になる可能性があるため、注意が必要です。
おとり広告によるリスク
おとり広告は、顧客からの信頼を大きく損なう手法です。おとり広告であることが公になれば、企業イメージを低下させることになり、これまで築いてきた良好な消費者との関係性を壊してしまうことになりかねません。
故意のおとり広告はもちろんですが、例えば、物件入力のミスや更新漏れなどであっても、おとり広告だと判断されれば罰則の対象になる可能性があります。
おとり広告の違反内容や程度によって、注意・警告・厳重警告・厳重警告と違約金の措置を段階的に受けることになります。最悪の場合、業務停止や宅地建物取引業の免許停止となる可能性もありますので、注意が必要です。
よくある「おとり広告」の事例
ここでは、「おとり広告」に該当する事例について紹介します。
例えば、すでに成約済みの物件を広告に掲載する行為、所有者が売却する意思がない物件を掲載することなどはおとり広告と判断されます。おとりの物件で興味関心を引き、問い合わせがあった際に「ついさきほど申し込みが入りました」と伝え、他の物件に誘導するといったケースがみられます。
また、実際の物件をより魅力的なものと誤認させるために、価格や間取り、写真などを意図的に不正確に掲載した場合も、おとり広告に該当します。「管理費込み」と広告に記載しながら、実際は「管理費別途支払い」といったケースも同様です。
おとり広告が発生する理由
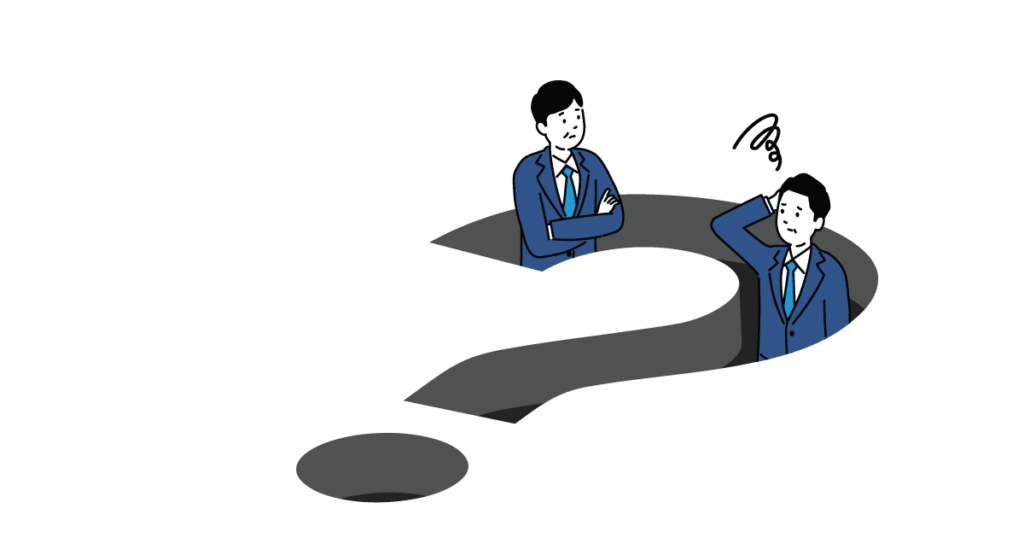
「おとり広告」が出稿される背景には、不動産業界の競争激化や集客至上主義といった背景のほか、物件情報の更新漏れ、担当者の知識不足なども考えられます。
以下のそれぞれの理由について、詳しく解説します。
- 不動産業界内での競争激化と集客至上主義
- 担当者の知識、モラルが不十分
- 人手不足による情報管理の漏れ
- 物件情報システムによる情報管理の漏れ
不動産業界内での競争激化と集客至上主義
不動産業界内での競争が激化しているため、問い合わせ数や集客数を増やすための手段として「おとり広告」を行ってしまうといったケースが少なくありません。限られた広告予算で、より多くの反響を獲得するためには、訴求内容を魅力的なものにしなければならないことが背景にあります。この傾向は、大手に比べて中小の不動産会社で顕著です。
言うまでもありませんが、おとり広告によって短期的な成果を得たとしても、中長期的な視点でみれば、消費者の信頼を失うリスクの方が大きいと考えられます。昨今では、SNSで口コミが拡散されるため、おとり広告で集客している事実が露見すれば、ブランドや企業の信頼性の低下につながります。
透明性の高い情報発信と誠実な顧客対応こそが、広告費を有効活用するための最良の戦略と言えるでしょう。
担当者の知識、モラルが不十分
広告出稿においては、担当者の経験や知識、倫理観が広告性の適格性に影響します。広告の適正基準や宅地建物取引業法の理解が不十分な場合、おとり広告と魅力的な広告の区別を履き違えてしまう可能性があるでしょう。
また、「多少の誇張は問題ない」「集客最優先」といった考え方が不動産業界内に残っていることも背景の一つと言えそうです。これらの理由から、広告に対する社内ルールがなく、担当者任せになっている企業では、意図の有無にかかわらず、おとり広告を出稿してしまうリスクが大きいと言えるでしょう。
人手不足による情報管理の漏れ
物件情報は常に変動するため、迅速な情報更新が求められます。しかし実態は、営業活動を最優先とする企業が多く、物件情報を更新する担当者のリソースが不足しているといったケースが少なくありません。そのため、成約済みの物件情報がホームページや不動産ポータルサイト上に掲載されたままになっているといったことがしばしばみられます。
特に多数の物件を抱えている、自社のホームページや不動産ポータルサイトの管理の担当者が兼務となっている場合は、情報管理が手薄になる傾向がありますので、注意が必要です。
物件情報システムによる情報管理の漏れ
物件情報システムが最新の情報に更新されていない、あるいは社内での情報共有がスムーズに行われないことで、最新の情報が反映されず、意図せずおとり広告になってしまうことがあります。
特に、SUUMOやアットホームなどのポータルサイトは、情報をリアルタイムに同期させることは難しいため、注意が必要です。というのも、ポータルサイトでは更新のタイミングが決められており、最新の情報が反映されるまでにどうしてもタイムラグが生じてしまうからです。
自社ホームページの情報をリアルタイムに更新していたとしても、広告を出稿したポータルサイトで最新情報をリアルタイムに反映できていないと、場合によってはおとり広告とみなされてしまうこともあるかもしれません。
ポータルサイト側の更新のタイミングを把握し、タイムラグを少しでも小さくするような工夫が必要と言えるでしょう。
おとり広告を防ぐためのポイント

おとり広告を防止するためには、広告掲載に関する社内ルールを策定し、社員に周知徹底するなどの対策が必要になります。
ポイントは以下のとおりです。
- 物件情報の確度を高める
- 広告表現を確認する
- 写真・画像を掲載する際のルールを徹底する
- 広告媒体の特性を踏まえて出稿する
- 広告担当者の研修を行う
- 国交省や業界団体のガイドラインを確認する
物件情報の確度を高める
情報の更新頻度を高め、成約済みや取り下げとなった物件の情報を速やかに削除するルールを設定しておきましょう。例えば、広告担当者と営業担当者がダブルチェックを行うと決めておけば、物件情報の削除漏れを防ぎやすくなります。
また、常に正確な情報が発信されているかどうかの確認も重要です。例えば、物件情報を確認する曜日・時間を決めておくといったチェック体制を整えましょう。
チェック体制を整えることで情報の正確性やコンプライアンスを保ちやすくなります。
広告表現を確認する
広告に掲載する内容や表現について、誇大広告や不当表示になってないかなどの確認を徹底するようにしましょう。例えば、他社物件と比較するような広告を行う際は、客観的なデータに基づいた正確な情報を使用しなければなりません。
また、広告に適した用語、使用を禁止されている用語などを理解し、不適切な表現は排除することも重要です。例えば、不動産広告において最上級を表す表現や主観的な表現は原則禁止されています。
以下の用語は、不適切な表現として使用が禁止されているもの、または慎重に扱う必要があるものの一例です。
- 完全、完璧、絶対
- 日本一、業界初
- 特選、厳選
- 最高級、抜群
- 格安、土地値、希少
- 完売、激安
- 広い、明るい
写真・画像を掲載する際のルールを徹底する
画像掲載は誤解を招いたり、消費者の誤認を誘導するおそれがあるため、掲載する場合は注意が必要です。
例えば、実物よりもよくみせるための加工や修正はNGです。電柱や電線などを消去したり、画像を明るくして陽当たりが良いようにみせるといったことはできません。
もし画像を加工する場合は、加工以前・以後の違いが分かるように、それぞれの写真を掲載しておくと良いでしょう。
パノラマ写真で物件を紹介するケースもありますが、実際の室内や間取りの印象と異なってしまうことがあります。広範囲をみせられることがパノラマ写真の強みではありますが、空間を一度に撮影するため、実際よりも広くみえてしまうといったことがあるようです。
パノラマ画像やCG画像などを利用する場合は、実際とは異なる可能性があることを明記するようにしましょう。広告を見た顧客が誤認しないように配慮することが求められます。
なお、車両のナンバープレートや表札の名前を消すなどは、プライバシーへの配慮から認められています。
広告媒体の特性を踏まえて出稿する
信憑性の高い広告媒体を選定し、適切な広告掲載を意識することが重要です。不動産ポータルサイトは物件情報の掲載条件や表現内容、更新頻度が定められていることが多く、虚偽や誇大表現が禁止されています。
また、不動産ポータルサイトによっては独自のルールを設けているケースもあります。例えば、複数の写真を組み合わせて掲載する、写真に文字を入れて合成することなどを禁止しているといったものです。厳格な審査基準を設けている各サイトのガイドラインを確認し、ルールに従って掲載していくことで、結果的におとり広告になってしまうといった事態を防ぐことができるでしょう。
広告担当者の研修を行う
広告担当者や広告を作成する可能性がある社員に対しては、広告に関する研修を定期的に実施し、適正な不動産広告の基準や法令順守についての理解を促すことが大切です。
研修は、座学だけでなく、実際の事例をもとにしたディスカッションやワークショップなども取り入れると効果的です。特にワークショップは、過去の広告事例をもとに、問題点についてグループで議論して判断力を養うことにつなげられます。実際に広告を作成するケーススタディを行うことで、適正な広告に関するより実践的な知見を得ることができるはずです。
担当者には問題意識を持って受講してもらい、実際に作業をしながら理解を促すことで、より効果を高めることができるでしょう。また、研修後も定期的にチェックを行い、学んだ内容を定着させることで、おとり広告防止の効果を高めることにつながります。
国交省や業界団体のガイドラインを確認する
国土交通省や消費者庁、不動産業界団体のホームページでは、不動産広告に関するガイドラインを策定して公開しています。
- 国土交通省
- 消費者庁
- 不動産公正取引協議会連合会
- 全日本不動産協会
- 全国宅地建物取引業協会連合会
特に業界団体では、会員向けの研修や相談窓口を設けていることもあり、不動産広告に関する法規制や業界ルールの正確な理解、把握に役立てることができます。
広告の入出稿を一括管理できるシステムを導入する
不動産物件広告の入出稿を一括管理することができるクラウドサービスを活用することで、業務効率はもとより、広告の管理をさらに徹底することができます。
例えば、複数の媒体に広告を掲載する場合、それらを一括管理することで、更新済み・未更新などの確認漏れなどを防ぐことが可能です。また、情報入力回数を減らすことで、人為的な入力ミスの確率を下げることができます。
『いい生活賃貸クラウド 物件広告』は、賃貸物件の情報を不動産ポータルサイトはもちろんのこと、REINS(レインズ)などの業者間流通サイトや、 FCシステムなどに一括掲載することが可能です。また全国の不動産会社が参加する賃貸業者間流通サイト「いい生活Square」から取り込んだ物件を、自社のホームページや各不動産ポータルサイトに自動でコンバート、セールスコメントも物件情報をもとに自然なPR文を自動生成しますので人為的な入力ミスを防ぐことができます。
『いい生活売買クラウド One』は、売却査定、顧客情報の管理などの一連の不動産売買業務のデジタル化をサポートします。SUUMOやアットホームなど、各不動産ポータルサイトへの一括出稿が可能なコンバート機能を実装するなど、不動産広告業務のサポートも手厚いことが特徴です。
おとり広告を防ぐためのポイントを整理する

おとり広告は、顧客からの信頼を失い、企業イメージを低下させるだけでなく、場合によっては法的責任を問われる可能性もあります。そのため不動産会社は、おとり広告の違法性を十分に認識し、コンプライアンス体制を強化することが求められます。社内における広告掲載基準の明確化を推進し、従業員における基準の周知徹底を強化し、おとり広告を未然に防ぐ体制を整備することが重要です。
加えて、おとり広告の防止には広告の入出稿の管理強化も有効です。『いい生活賃貸クラウド 物件広告』、『いい生活売買クラウド One』などの不動産業務のデジタル化をサポートするツールを活用することで、おとり広告の防止と業務効率化を同時に実現することができます。ぜひ、ご検討ください!


